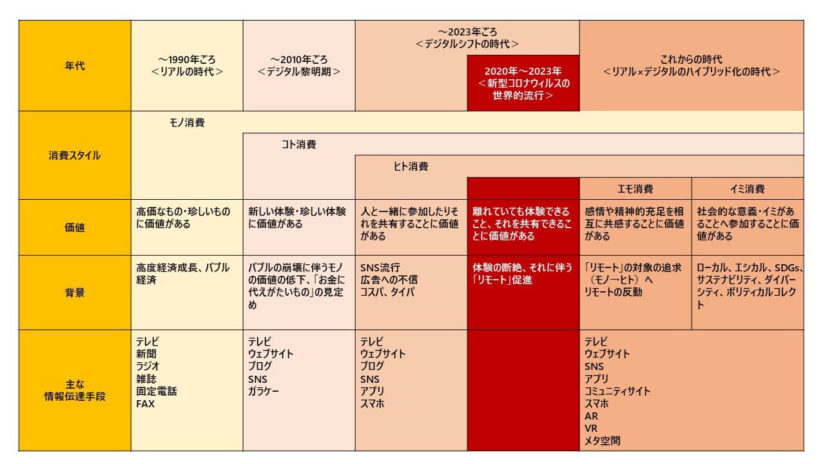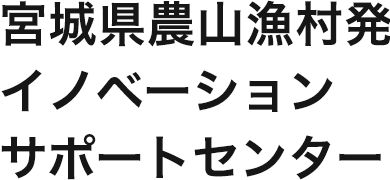ブランド戦略とは、ブランディングを行うための戦略のことを言い、ブランディングの対象を大まかに分類すると「インナー」と「アウター」の2方向があります。
インナーブランディングとは社員や役員など自社の従業員に向けて行うブランディングで、アウターブランディングとは、顧客や取引先、投資家などといった「社外」に向けたブランディングです。
ブランディングとは、対象となるステークホルダーに向けて共通したイメージを持ってもらうことを目的に行います。
——なぜブランド戦略が必要なのか
ブランド戦略を立てて、自社や商品のブランディングを行うことには、様々なメリットがあります。
大きく分けると下記3点です。
1.価格を自社でコントロールできる
2.他社との差別化がなされ、競争力が高くなる
3.商品やサービスが勝手に売れるようになる
一つずつをさらに掘り下げていきましょう。
1.価格を自社でコントロールできる
例えば車を想像してみてください。普通車やスポーツカー、高級車など、世の中には様々な車が販売されています。そのどれもが大なり小なりブランディングを行っておりますが、特に高級車ラインと言われる車の中には青天井と言われるほど高く、リセールバリューも非常に高い車が存在します。パーツや性能が他の高級車と大きく違うわけでもないのに、販売価格が高い車の背景には、これまで数十年と弛まず築いてきたブランド力があります。1,000万円で作った車を1億円で販売をしたとしても「欲しい!」と思わせれば、それには9,000万円のブランド付加価値があり、価格の決定権を消費者ではなく企業が持てるようになります。これがブランディングを行うべき1つ目の理由です。
2.他社との差別化がなされ、競争力が高くなる
同じく車の例で考えてみましょう。高級車を販売しているメーカーは数多く存在します。一方で、消費者は様々なメーカーが販売している様々な高級車を比較検討します。群雄割拠している同じ価格帯の商品ラインナップから自社商品を選んでもらうためには、値段以外の価値を感じてもらう必要があります。この「値段以外の価値」こそがブランドであり、この価値を高めることで商品の競争力が高くなります。これがブランディングを行うべき2つ目の理由です。
3.商品やサービスが勝手に売れるようになる
適切なブランディングを行うと、消費者が自社商品の良いところを能動的に見つけてくれます。そして、その良いところが競争力を高める要因となり、何もしなくても商品やサービスが勝手に売れ出す、善循環を作り出すことに繋がります。これはマーケティングに通ずる部分もあります(マーケティング=何もしなくても商品が売れる環境づくり)。
数十年とブランディングを行ってきたメーカーの車は、その社名を聞いただけで「高級だよね」「質感が良いよね」というような感想を抱くはずです。値段が高くとも、高級なブランド力に惹かれて購入する人たちは、このメーカーが培ってきたブランドを買っていることと等しいのです。これがブランディングを行うべき3つ目の理由です。
上記3点のようなメリットを生み出すべく、ブランディングをより効果的に行うための考え方が「ブランド戦略」です。
——ブランド戦略にフレームワークを用いる理由
ブランド戦略にフレームワークを用いる理由は、既出の通り「ブランディングを効果的・効率的に行えるから」です。このフレームワークには実に様々な種類があり、日々新しい考え方が生まれておりますが、ここでは代表的な分析方法を3つお伝えします。
1.PEST分析
PEST分析とは、自社を取り巻く外部環境が、現在もしくは将来的にどのような影響を与えるかを把握・予測するためのフレームワークのことです。 「政治(Politics)」 「経済(Economy)」 「社会(Society)」 「技術(Technology)」のそれぞれの頭文字を取ってPEST分析と呼ばれます。これら4つの外部環境の要素を取り出し、分析対象とします。
2.STP分析/3C分析/4P分析
STP分析とは、競合他社との位置関係を把握・決定することができるフレームワークです。S=「市場の細分化(Segmentation・セグメンテーション)」、T=「ターゲット層の抽出(Targeting・ターゲティング)」、P=「競合との差別化(Positioning・ポジショニング)」を表した言葉です。各段階において、それぞれの役割があります。まずセグメンテーションで市場の全体像を把握し、ターゲティングでその中から狙うべき市場を決定し、ポジショニングで競合他社との位置関係を決定することができます。
3C分析とは、市場環境を分析するフレームワークのことです。 3C分析は「顧客(Customer)」 「自社(Company)」 「競合他社(Competitor)」の3つを軸にして市場環境を分析するフレームワークです。 おもにマーケティング戦略の策定や、事業計画に用いられます。
そして、4P分析とは、自社商品・サービスにまつわる「商品(Product)」 「価格(Price)」 「流通(Place)」 「販売促進(Promotion)」の、4つの頭文字をとったマーケティング手法です。 この4つの戦略領域を分析することで、具体的なマーケティング戦略を立案できます。
よくある間違いがSTP分析の前に3C分析や4P分析をしてしまう、という例です。4P分析の方が普段の業務との被りもありとっつきやすいので、どうしても先に考えてしまいがちです。しかし、正しいSTP分析を行って自社の現在地を把握した上で3C分析や4P分析を行わないと、その後のブランド戦略が絵に描いた餅になってしまうので注意しましょう。
3.SWOT分析
SWOT分析とは、自社の内部環境と外部環境を、「強み(Strength)」 「弱み(Weakness)」 「機会(Opportunity)」 「脅威(Threat)」として洗い出し、分析する手法で、企業や事業の現状を把握するためのフレームワークです。
このようなフレームワークを場面に応じて活用しながら、ブランド戦略を練ることがより良いブランドを作り出すための最短ルートです。ここで間違ってはいけないのは、このようなフレームワークを用いるやり方は「つまらない失敗を防ぐ」効果がありますが、「必ず成功する」わけではない、ということです。
——まとめ
ブランディングは、企業自体や商品・サービスの認知度を高め、その価値を広く浸透させる活動です。 一方、マーケティングは、市場において商品やサービスが売れる仕組みをつくる活動です。 ブランディングとマーケティングは関連し合いながら、市場における優位性の確保に貢献し、企業経営を安定化させます。この記事では、その中でもブランディングにフォーカスし、初歩的な解説をしました。これからブランディングに挑戦される方々のお力になれれば幸いです。